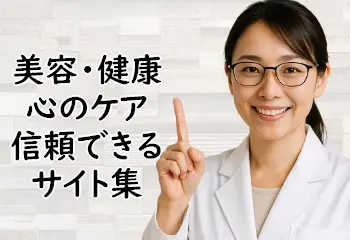短い秋も終わり徐々に冬に近づいていきます。こんな季節の変わり目から冬にかけては、毎日の食べ物が体調や冷え性に大きな影響を与えます。体を内側から温める食べ物を意識して選ぶことで、冷え性の対策をすることができます。
【この記事のポイント】
- 冷え性対策の食べ物の特徴と、避けた方がよい食べ物の違いがわかる
- 東洋医学の視点から冷え性対策の食べ物のヒントが得られる
- 冷え性の原因別に適した食生活のポイントを具体的に紹介
- 日常生活に取り入れやすい冷え性の対策方法とよくある疑問をQ&A形式で解説
冷え性対策として押さえておきたい食べ物の基本と栄養素

体を温める食材とは?冷えやすい食材との違いに注目
体が冷えやすいと感じるとき、まず見直したいのが食べ物の選び方です。体を温める食べ物としてよく知られているのは、根菜類(ごぼう、にんじん、れんこんなど)や生姜、にんにく、唐辛子など。これらは血行を促進し、内臓からじんわりと温める働きがあるとされています。特に、火を通して調理された料理は体への負担が少なく、冷えの改善にもつながりやすいです。
反対に、冷たい飲み物や南国産の果物(バナナ、パイナップル、スイカなど)、生野菜ばかりの食生活は、体を内側から冷やしてしまう要因になります。忙しい朝に冷たいヨーグルトだけで済ませていませんか? その習慣が冷え性の一因になっているかもしれません。
POINT:根菜や香味野菜を温かく調理し、冷たい食べ物は控えめにするのが冷え対策の第一歩です。
「陽性食品」を取り入れる食事法とは?東洋医学に学ぶ体の整え方
東洋医学では、食材には「陰」と「陽」の性質があると考えられています。中でも陽性食品は、体を温めてエネルギーを巡らせる働きがあるとされ、冷えやすい体質の方には特に取り入れたい存在です。たとえば、生姜、ねぎ、にんにく、シナモン、味噌などがその代表格。日々の食事に少しずつ取り入れることで、体の内側からの冷えにアプローチできます。
一方で、きゅうりやナス、トマトといった夏野菜は陰性食品に分類され、体を冷やしやすい傾向があります。これらは温かいスープや炒め物にすることでバランスを取ることが可能です。「どちらか一方だけに偏る」のではなく、季節や体調に合わせて食材の陰陽バランスを意識することが大切です。
POINT:東洋医学をヒントに、陽性食品を中心とした温かい食生活を意識してみましょう。
▶冷え性の原因を女性特有の視点で解説|体質改善の第一歩に の記事はコチラ
代謝を高めるための調理法と食材の選び方
冷え性の改善には、食材の性質だけでなく「どう調理するか」も重要なポイントです。せっかく体を温める食材を選んでも、生で食べたり冷たい状態で摂取しては効果が半減してしまいます。おすすめは、スープや煮込み料理、グリル、蒸し物など、体の内側から温まる調理法です。
また、代謝をサポートするには、温かい朝食からスタートするのが理想的。白湯やスープで内臓を目覚めさせることで、1日の代謝スイッチが入りやすくなります。間食としても、冷たいアイスやスナックではなく、ナッツや温かいお茶などを選ぶことで、体温のキープに一役買ってくれます。
POINT:温かい料理+1日を通じた“冷やさない食習慣”が代謝アップの鍵です。
冷えに負けない体をつくるビタミン・ミネラルの基礎知識
鉄分、亜鉛、ビタミンB群、マグネシウムといった栄養素は、血液の巡りや代謝を支えるうえで欠かせない存在です。女性は特に鉄分不足になりやすく、これが原因で血行不良や低体温につながるケースも。日々の食事でこれらの栄養素をしっかりと補うことが、冷え性の根本改善につながります。
| 栄養素 | 多く含む食材 |
|---|---|
| 鉄分 | レバー、赤身肉、ひじき、大豆製品 |
| 亜鉛 | 牡蠣、豚レバー、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 卵、魚、玄米、きのこ類 |
| マグネシウム | アーモンド、海藻、納豆 |
これらの栄養素を毎日の食事に少しずつ取り入れることが、めぐりのよい体づくりに役立ちます。特に忙しい方は、手軽に摂れるスープや具だくさん味噌汁にこれらの食材を活用すると続けやすくなります。
POINT:ミネラルやビタミンを含む食材を、温かい料理に取り入れて毎日の習慣に。
冷え性の原因別の食べ物でできる対策方法

「血行不良型」冷え性におすすめの食材と摂り方
「血行不良型」の冷え性は、主に筋肉量の低下や運動不足、長時間同じ姿勢でいることなどが原因で、血液の循環が滞るタイプです。特に下半身の末端冷えに悩む方が多く、手足の先が氷のように冷たくなることも。このタイプの冷えを和らげるには、血流を促進する栄養素や食材を積極的に取り入れることが大切です。
おすすめの食材には、青魚(サバ、イワシ、サンマなど)に豊富なEPAやDHA、にんじん・ごぼう・かぼちゃなどの根菜類、生姜やにんにくといった香味野菜があります。これらは体を温める効果と同時に、血管を拡張し血の巡りをスムーズにする働きが期待されています。また、ビタミンEを多く含むアーモンドやアボカド、かぼちゃなども、末端までしっかりと血液を届けるサポートに役立ちます。
さらに食べ方としては、温かいスープや煮物、蒸し料理などで体を冷やさないよう意識しながら、ゆっくりよく噛んで食べることもポイントです。
POINT:血流を促す青魚やビタミンE豊富な食材を、温かい料理で取り入れることが血行不良型の冷え対策に効果的です。
▶風呂上がりのヘアケアの正しい順番とおすすめアイテムで翌朝もまとまる髪に の記事はコチラ
「内臓冷え型」に効果的なあたたかい食習慣
手足はそれほど冷たくないのに、なんだか体の中心が冷えているように感じる――そんなタイプは「内臓冷え型」の可能性があります。このタイプは、冷たい飲食物の摂りすぎや、冷房環境、薄着などによって内臓温度が低下し、代謝が落ちてしまうのが特徴です。冷えが長引くと胃腸の働きが低下し、便秘や食欲不振、疲れやすさにつながることも。
内臓を温めるには、まずは温かい飲み物を日常に取り入れるのが基本。白湯や生姜湯、味噌汁などが体にやさしく働きかけます。また、雑炊や煮込みうどん、根菜のスープなど消化に良くて温かい料理もおすすめです。食材では、長ねぎ、にら、生姜、にんじん、かぼちゃなどが内臓に負担をかけず温めてくれる代表格。
冷たい飲み物は控え、食事は「温かいものをゆっくり食べる」ことを意識するだけでも、内臓の冷えをやわらげる効果が期待できます。
POINT:体の中心からじんわり温めるには、生姜や根菜を使った消化の良い温かい料理が効果的です。
「自律神経型」冷えに効く食べ物と注意したいこと
ストレスや生活リズムの乱れ、睡眠不足が重なると、自律神経が乱れて体温調節がうまくいかなくなることがあります。これが「自律神経型」の冷え性。体の外側は冷えていなくても、気づかないうちに“なんとなく寒気がする” “手足だけが冷たく感じる”といった感覚を持つことが多いのが特徴です。
このタイプの冷えにアプローチするには、まずは自律神経を整えるビタミンB群やマグネシウム、カルシウムなどの栄養素を積極的に摂ることが有効です。ビタミンB群は豚肉、卵、きのこ類に多く含まれ、マグネシウムは納豆や海藻類、アーモンドなどに豊富です。
また、血糖値の急上昇・急降下は自律神経を乱す原因になるため、砂糖を多く含むスイーツや清涼飲料水は控えめに。間食には温かいお茶やナッツ類、ゆで卵などを選ぶとよいでしょう。
POINT:栄養バランスを整えることが、自律神経の乱れによる冷え対策のカギになります。
「筋肉不足型」冷えにアプローチする高たんぱく食材とは
加齢や運動不足によって筋肉量が減少すると、体内で熱を生み出す力が低下します。これが「筋肉不足型」の冷え性で、特に痩せ型の女性や運動習慣が少ない人に多く見られます。このタイプは、食事から筋肉の材料となるたんぱく質をしっかりと摂ることが大切です。
おすすめの高たんぱく食材は、鶏むね肉、鮭、卵、大豆製品(豆腐、納豆、厚揚げなど)、乳製品。特に大豆食品は、女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンも含まれており、冷えだけでなくホルモンバランスのケアにもつながります。
また、たんぱく質を効率的に吸収するためには、ビタミンB6(マグロ、バナナ、にんにくなど)も一緒に摂ることがポイント。温かい鍋料理やスープにこれらの食材を取り入れると、手軽にバランスの良いメニューが完成します。
POINT:筋肉量を増やす高たんぱく食材は、冷え対策と代謝アップの両面で効果的です。
冷え性対策に役立つ食べ物の取り入れ方とQ&A

ここでは、冷えを感じたときに役立つ食べ物の選び方や日常での実践方法について、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。無理なく続けられる冷え対策のヒントが見つかるはずです。
冷え性対策に効く食べ物Q&Aでよくある疑問を解消
Q1. 朝食を食べる時間がない日は何を食べるのがベスト?
A. 朝に体温を上げるには、白湯や温かいスープ、ゆで卵やおにぎりなど簡単でも温かいものを選ぶのが理想です。冷たいヨーグルトやジュースは避けた方がよいでしょう。
Q2. コンビニで買える冷え対策に向いた食品は?
A. 具だくさんの味噌汁、温めたおでん、ゆで卵、ナッツ、ホット飲料などが便利です。冷たいサラダやスイーツではなく、温かく体にやさしいものを選びましょう。
Q3. 毎日スープを作るのが面倒なときの対策は?
A. 作り置きできる「冷凍スープ」や、具材入りの即席みそ汁を常備しておくと便利です。インスタントでも根菜や生姜入りのものを選ぶと、体を温める助けになります。
Q4. 生野菜が好きだけど冷えるって本当?
A. はい、生野菜は体を冷やしやすいため、冷え性が気になる方は加熱した温野菜にするのがおすすめです。レンジで軽く蒸すだけでも、胃腸の負担が軽減されます。
Q5. スイーツがやめられないけど冷えに悪い?
A. 白砂糖を多く含む冷たいスイーツは、血糖値の急上昇と冷えの原因になります。代わりに、温かい焼き芋や甘酒、黒糖を使った和菓子などに置き換える工夫が◎。
Q6. 夏でも冷えを感じるときの食べ物選びは?
A. 暑い時期でも内臓が冷えている方は多く、アイスや冷たい飲料を控えることが大切です。常温以上の飲み物や、生姜入りのスープを継続して取り入れましょう。
日々のちょっとした工夫でも、冷えにくい体へと変わっていけます。Q&Aで紹介したポイントを参考に、自分に合った方法から始めてみてください。
▶貧血とストレスの関係を見逃さないで「なんとなく不調…」はサインかも? の記事はコチラ
冷え性対策に効果的な食べ物を使ったレシピ紹介
体を芯から温めてくれる食材を使った、簡単で栄養バランスの取れた2品のレシピをご紹介します。冷えを感じる朝や疲れた日の夜に、手軽に取り入れられる温活メニューです。
生姜たっぷり根菜スープ(2人分)
材料
- にんじん…1/2本(約60g)
- 大根…5cm(約100g)
- ごぼう…1/2本(約60g)
- 生姜(千切り)…1片分
- だし汁…400ml(既製品の顆粒和風だしでOK)
- 薄口しょうゆ…大さじ1
- みりん…小さじ1
- 塩…少々
作り方
- にんじん、大根は皮をむいて薄い半月切りに、ごぼうはささがきにして水にさらす。
- 鍋にだし汁を入れて火にかけ、すべての野菜と生姜を加える。
- 野菜がやわらかくなるまで中火で約10分煮る。
- 薄口しょうゆ、みりん、塩で味をととのえたら完成。
POINT:生姜と根菜の組み合わせで、体の芯からぽかぽかに。冷え性対策にぴったりの和風スープです。
豆腐ときのこのあんかけ丼(2人分)
材料
- 絹ごし豆腐…1丁(300g)
- しめじ…1/2株(約50g)
- しいたけ…2枚
- 長ねぎ(斜め切り)…1/3本
- だし汁…200ml(既製品の顆粒和風だしでOK)
- しょうゆ…大さじ1
- みりん…大さじ1
- 片栗粉…小さじ2(水大さじ1で溶く)
- 温かいご飯…2膳分
作り方
- 豆腐はキッチンペーパーで包み、10分ほど水切りしておく。
- しめじは小房に分け、しいたけは薄切りにする。
- 鍋にだし汁を入れて火にかけ、きのこ類と長ねぎを加えて5分煮る。
- しょうゆ・みりんを加え、水溶き片栗粉でとろみをつける。
- 豆腐をスプーンで大きめにすくって丼に盛り、きのこあんをたっぷりかける。
POINT:たんぱく質豊富な豆腐と、代謝を支えるビタミンB群を含むきのこを使ったあんかけ丼。胃腸にやさしく温まる一品です。
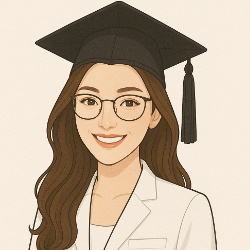
「冷え性は食習慣から変わる」を実感中。朝の白湯や根菜スープを続けるだけで、冬の手足の冷えがぐんとラクに。冷えない体は、毎日の積み重ねからです。