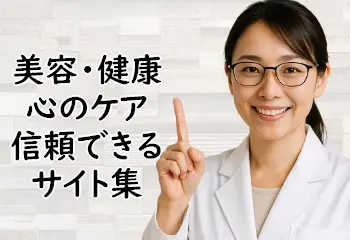疲れやすい、気分が落ち込みやすい、骨の健康が気になる…。そんなときに注目したいのがビタミンD。不足しやすい栄養素ですが、記事で紹介をしているビタミンDを含むおすすめ食品を取り入れることで、体も心も健やかに整えやすくなります。
【この記事のポイント】
- ビタミンDの基本と不足で起こりやすい不調を解説
- 魚介類・きのこ・卵・乳製品・乾物などビタミンDを含むおすすめ食品を種類別に紹介
- ビタミンDの不足分をサプリで補うときのおすすめの選び方と注意点
- 食品やサプリでビタミンDを摂る生活をしている女性たちの体験談を掲載
ビタミンD不足のリスクを知って多く含むおすすめ食品で補おう

ビタミンDとは?全身の健康を支える“調整役”の栄養素
ビタミンDは脂溶性ビタミンのひとつで、カルシウムやリンの吸収を助けて骨や歯を強く保つ働きから「骨のビタミン」とも呼ばれています。でも役割はそれだけにとどまりません。筋肉の維持や免疫力の調整、さらにはメンタルバランスや睡眠の質にも関わるなど、体全体の調整役として改めて注目されている栄養素です。
種類は大きく2つ。植物性食品に含まれる「ビタミンD2(エルゴカルシフェロール)」と、動物性食品や皮膚合成によって得られる「ビタミンD3(コレカルシフェロール)」です。特にD3は、紫外線を浴びることで皮膚で合成されるため、屋外活動の量や紫外線対策の影響を大きく受けます。
厚生労働省が定める成人女性のビタミンD推奨摂取量は、1日あたり9.0μg。ところが現代のライフスタイルでは、日光を浴びる時間が不足しやすく、食品から意識的に摂らなければ目標に届かないことも多いです。そのような方はビタミンDを含む食品を取り入れることをおすすめします。
さらに最近の研究では、ビタミンDが感染症予防や自己免疫疾患のリスク低下、さらにはうつ症状との関連にも注目され、美容や健康にとどまらずメンタルケアの観点からも関心が高まっています。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| ビタミンDの主な働き | カルシウム・リンの吸収促進/骨や歯の形成/筋肉維持/免疫調整/メンタル・睡眠サポート |
| 種類 | D2(植物由来)/D3(動物由来)※D3は紫外線で皮膚合成 |
| 注目される効果 | 感染症予防/自己免疫疾患リスク軽減/うつ症状との関連 |
| 推奨摂取量(成人女性) | 1日あたり9.0μg(厚生労働省推奨) |
| 摂取のポイント | 日光浴が少ない人は特に、ビタミン d 含む 食品 おすすめを意識 |
▶NMNサプリのおすすめポイントと選び方|エイジングケア世代の新習慣 の記事はコチラ
なぜ女性はビタミンD不足になりやすいのか?現代生活との関係
現代女性のライフスタイルには、ビタミンD不足の落とし穴がたくさんあります。美白志向や紫外線対策から日焼け止めを常用する人が増え、皮膚でのビタミンD合成が大幅に低下。さらに屋外活動の減少も影響しています。
加えて、在宅ワークやインドアな趣味の広がりで日光に当たる時間はますます少なくなっています。食生活においても、魚や卵、乳製品、きのこなどビタミンDを含む食品の摂取が不足しがちで、気づかないうちに欠乏していることも少なくありません。
―女性がビタミンD不足になりやすい主な原因―
| 主な原因 | 影響・説明 |
|---|---|
| 日焼け止めの常用 | 紫外線を遮断し、皮膚でのビタミンD合成を妨げる |
| 屋内中心の生活 | 日光を浴びる機会が少なく、D3の生成が不足 |
| 魚や乳製品をあまり摂らない | ビタミン d 含む 食品 おすすめを食べる機会が減り不足につながる |
| 年齢による皮膚機能の低下 | 加齢とともに合成力が低下 |
| 妊娠・更年期などのホルモン変化 | 骨代謝の変動により需要が増す |
このように、現代の生活習慣にはビタミンD不足のリスクが潜んでいます。美容や健康を維持するためには、日常的にビタミンDを含む食品を意識して取り入れることが欠かせません。
▶デトックス食材で内側からキレイに!レシピや効果的なやり方も紹介 の記事はコチラ
ビタミンD不足のサインは?不調を見逃さない対策
ビタミンDが不足すると、私たちの体にはさまざまな不調が現れます。しかしそれがビタミンDの欠乏によるものと気づかず、放置されてしまうケースも少なくありません。以下は、ビタミンD不足により起こりやすい代表的な症状です。
| 不調のサイン | 考えられる影響 |
|---|---|
| 骨密度の低下・骨折リスクの上昇 | カルシウム吸収不全による骨の弱体化 |
| 筋力低下・慢性的な疲労感 | 筋肉や神経伝達への影響 |
| 風邪をひきやすい・感染症への脆弱性 | 免疫細胞の機能低下 |
| 気分の落ち込み・睡眠障害 | セロトニン・メラトニン代謝との関係が指摘されている |
これらの不調を感じた場合は、まず日常の生活習慣を見直すことが大切です。朝や昼間に15〜30分ほどの日光を浴びる、ビタミンDを含む食品を毎日の食事に取り入れる、必要に応じてサプリメントを使うなど、できることから始めてることをおすすめします。
また、血液検査でビタミンD濃度を確認することで、自分に不足があるかを客観的に知ることができます。不安な方は医師や管理栄養士に相談して、適切な対応を心がけましょう。
ビタミンDを含むおすすめ食品を食材別に紹介

魚介類はビタミンDを含むおすすめ食品の代表|種類と調理のコツ
ビタミンDを含む食品の中でも、魚介類はまさに王道。特に脂がのった青魚や干物はビタミンDが豊富で、効率よく摂取できるのが魅力です。サケやサンマ、いわし、まぐろはスーパーでも手に入りやすく、調理がしやすいから忙しい毎日でも取り入れやすいです。
ビタミンDは脂溶性ビタミンなので、油を使った調理との相性が抜群。ムニエルやソテー、炒め物にすれば吸収率がアップして、美味しさも一段と引き立ちます。さらにカルシウムを多く含む食材と組み合わせると、骨の健康を守る働きも期待できます。
【主な魚介類のビタミンD含有量(100gあたり)】
| 魚介類 | ビタミンD含有量(μg) | おすすめの調理法 |
|---|---|---|
| サケ(焼き) | 32.0 | 塩焼き、ムニエル、スモークサーモン |
| さんま(焼き) | 16.0 | 内臓ごと焼けば、さらに栄養価アップ |
| まぐろ(赤身) | 6.0 | 刺身や漬け丼でさっぱりと楽しめる |
| いわし(丸干し) | 50.0 | 焼き魚はもちろん、常備菜にしても便利 |
【POINT】μg(マイクログラム)とIU(国際単位)の違い
μg(マイクログラム)は重さの単位で、1μg=100万分の1グラム。一方、IU(国際単位)は栄養素の「効力」を示す単位で、ビタミンDの場合は1μg=40IUに換算されます。たとえば10μgは400IU。両方の単位を知っておくと、サプリ選びや食品表示がもっとわかりやすくなるはず。
ビタミンDを含む食品を効果的に取り入れるなら、魚料理を週に2〜3回メインにするのがおすすめ。缶詰や冷凍魚を常備しておけば、忙しい日でもサッと調理できて、無理なく続けやすくなります。
▶女性に多い背中ニキビの原因とブツブツの正しい治し方 の記事はコチラ
きのこ類もビタミンDを多く含むおすすめ食品|種類と調理のコツ
きのこ類は、植物性のビタミンD2を含む食品として知られています。カロリーが低いのに栄養価が高く、女性の美容や健康維持にもうれしい存在。まいたけ、しめじ、エリンギなどはスーパーで手に入りやすく、どんな料理にも合わせやすいのが魅力です。
ビタミンDは脂溶性のため、油を使った調理で吸収率が高まります。オリーブオイルやごま油で炒めたり、バターでソテーにすれば、香りも良く食欲をそそる一皿に。加熱による損失が少ない栄養素なので、火を通しても安心して摂取できます。
さらにおすすめしたいのが、他の食材との組み合わせ。カルシウムを含む乳製品や、たんぱく質を多く含む食品と一緒に取り入れると、骨の健康維持につながります。たとえば、しめじ入りのクリームシチューや、まいたけのバター炒めにチーズを合わせたトーストなどは、満足感もあって栄養バランスが整います。
【よく使われるきのこ類と調理ポイント】
| きのこ類 | ビタミンD含有量(μg/100g) | おすすめの調理法 |
|---|---|---|
| まいたけ | 4.9 | 炒め物にして油と合わせると吸収率がアップ |
| しめじ | 1.0 | スープや味噌汁、リゾットなど汁物との相性が良い |
| エリンギ | 1.2 | ステーキ風に焼いて、食感の良さを楽しむ |
| えのき | 0.5 | 鍋やホイル焼きで、他の食材と一緒に味わえる |
特にまいたけはビタミンD含有量が多く、香りや食感も豊か。炒め物や和風パスタに使えば、料理に奥行きが出ます。下ごしらえでは水洗いを控えめにして、石づきを落とす程度にとどめることが、美味しさと栄養を保つコツです。
▶食物繊維はダイエットに効果あり?おすすめ食材とレシピで無理なく痩せる の記事はコチラ
卵や乳製品もビタミンDを含むおすすめの食品|手軽に摂取するコツ
魚やきのこが苦手でも安心。卵や乳製品も、手軽にビタミンDを取り入れられるおすすめの食品です。卵黄には1個あたり約1.1μgのビタミンDが含まれていて、毎日の食卓に無理なく加えやすいのがポイント。しかも全卵を食べれば、ビタミンDに加えてたんぱく質や鉄分、ビタミンB群までまとめて摂取できます。
乳製品では、チーズやバターのような高脂肪タイプにビタミンDが比較的多く含まれています。ビタミンDは脂溶性なので、こうした食品を通して摂ることで吸収効率も高まります。牛乳自体は少なめですが、最近は「ビタミンD強化牛乳」などの商品もあり、補助的に使うと栄養バランスが整いやすくなります。
【卵・乳製品に含まれるビタミンD量(100gあたり)】
| 食品 | ビタミンD含有量(μg) | 取り入れ方の例 |
|---|---|---|
| 卵黄(1個分:約17g) | 約1.1 | ゆで卵、目玉焼き、オムレツ |
| チェダーチーズ | 0.4 | トーストやサラダ、グラタンにプラス |
| カマンベールチーズ | 0.6 | ワインのおつまみやサンドイッチに |
| ビタミンD強化牛乳 | 1.2(製品による) | 朝食や間食に1杯取り入れる |
| バター | 0.8 | パンや料理の風味づけに使う |
朝食にチーズトーストとゆで卵を合わせたり、間食でヨーグルトを選んだり。ほんの少し意識するだけで、毎日ビタミンDを摂りやすくなります。続けやすい食品だからこそ、日常の習慣に取り入れることが健康の第一歩につながります。
乾物もビタミンDを含む食品として外せない|保存食としての活用術
効率よくビタミンDを摂りたいなら、乾物は外せない食材です。きのこや魚介を乾燥させた食品は、栄養が凝縮されて保存性も高いのが魅力。忙しい毎日でも手軽に取り入れやすく、現代女性の頼れるストック食材になります。
きのこ類では、干ししいたけや乾燥きくらげが代表的。特に天日干しによってビタミンD2の含有量が生の数倍以上に増えることが知られています。魚介の乾物では、しらす干しや煮干し、ちりめんじゃこが定番。カルシウムも一緒に摂れるため、健康意識の高い女性におすすめの食品です。
【ビタミンDが豊富な乾物食品(100gあたり)】
| 食品 | ビタミンD含有量(μg) | 特徴・活用法 |
|---|---|---|
| 干ししいたけ(天日干し) | 12.7 | スープや煮物、炊き込みご飯にプラス |
| 乾燥きくらげ | 85.0 | 水で戻して炒め物や中華スープに活用 |
| しらす干し | 61.0 | 大根おろしやパスタ、卵焼きにトッピング |
| 煮干し | 50.0 | だし取りはもちろん、粉末にしてふりかけ代わりにも |
乾物は水で戻すだけで使えるから、時短調理にもぴったり。冷蔵庫や棚に常備しておけば、天候や買い物のタイミングに左右されず、安定してビタミンDを摂れるという利点があります。まとめ買いしてストックしておくと、毎日の食事作りがスムーズになります。
▶漢方で肌荒れを改善へ|乾燥・かゆみ・ニキビ・むくみをケア の記事はコチラ
おすすめのビタミンDを含む食品とサプリの併用法

ビタミンDを含む食品だけで足りないときのサプリ活用術
普段の食事でビタミンDを意識していても、実際には必要量に届かないケースは珍しくありません。特に魚や卵をあまり食べない方、紫外線を避ける生活をしている方、そして冬場など日照時間が短い季節は、体内のビタミンDが不足しやすい状況になります。
そんなときに役立つのが、ビタミンDのサプリメント。毎日一定量を安定して補えるので、食事内容に左右されずに摂取できるのが大きな魅力です。妊娠中・授乳中や更年期など、骨密度や免疫機能が気になる時期の女性にとっても、心強い栄養サポートになります。
ただし、サプリはあくまでも“補助”の役割。ビタミン d を含む食品をおすすめ基本に、足りない分をサプリでカバーするのが理想です。ライフスタイルや体調に合わせて、自分に合った摂取バランスを工夫しましょう。
【POINT】
サプリメントは「食品からの摂取+不足分の補助」として使うのが正解。
ビタミンDを含むおすすめの食品を食習慣として取り入れつつ、必要に応じてサプリで安定的に補うことが、長く続けられる秘訣です。
ビタミンDサプリの選び方|成分・含有量・相性栄養素に注目
サプリを選ぶ際には、成分や含有量、安全性をしっかり確認することがポイントです。特に注目したいのが「ビタミンD3(コレカルシフェロール)」を含むかどうか。ビタミンDには植物性のD2と動物性のD3がありますが、体内での利用効率が高いのはD3といわれています。
さらに、1日の摂取量が適正であるかも重要です。目安は1粒あたり10〜25μg(400〜1,000IU)程度。含有量が多すぎるものは過剰摂取につながるため注意が必要です。加えて「カルシウム」「マグネシウム」「ビタミンK2」など、骨の健康に関わる栄養素と一緒に配合されたタイプを選ぶのもおすすめ。こうした組み合わせなら、相乗効果が期待できます。
【ビタミンDサプリの選び方まとめ】
| 選び方のポイント | 具体的な内容 |
|---|---|
| 成分の種類 | D2より吸収効率の高い「D3(コレカルシフェロール)」配合を選ぶ |
| 1日の目安量 | 10〜25μg(400〜1,000IU)が理想。過剰摂取には注意 |
| 相性のよい栄養素 | カルシウム、マグネシウム、ビタミンK2との組み合わせで効果的 |
| 安全性 | 国内製造、GMP認証、無添加設計などのチェックが安心 |
また、製造元の信頼性も見逃せません。「どんな原料で、どこで作られているか」にまで目を向けると安心感が違います。毎日続けるものだからこそ、品質と安全性を大切に選びたいですね。
ビタミンDを含むおすすめ食品を取り入れている方の体験談
実際にビタミンDを意識した生活を続けている人の声は、とても参考になります。最近ではSNSでも「#ビタミンD生活」や「#骨活」といったハッシュタグが広がり、ビタミンDを含む食品のおすすめ活用法や感想が多くシェアされています。
「干ししいたけのスープとサケのグリルを週2回。さらにビタミンDサプリを1日1粒で安心感もプラスしています」
(30代女性/Instagram)「在宅ワークで日差しを浴びる時間がゼロだから、ビタミンDサプリは欠かせません。最近は気分も安定してきた実感があります」
(40代女性/X)「妊活中なので、ビタミンDとカルシウムが一緒に入ったサプリに切り替えました。食事では卵やきのこなど、ビタミンDを含むおすすめ食品を食べることを意識しています」
(20代女性/Threads)
このように、食品とサプリをライフスタイルに合わせて上手に組み合わせる人が増えています。自分に合った方法でビタミンDを取り入れることが、無理なく続けられるコツ。まずは「食べる+補う」のシンプルな習慣から始めてみるのをおすすめします。
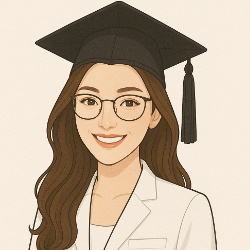
日常の食事に少しの工夫を加えるだけで、ビタミンDはしっかり補えます。魚やきのこ、乾物などの身近な食材を活用して、内側から健康と美しさを育てましょう。